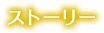- 【主人公】
- 「……わたし、帰りますね。一条寺くんは少しゆっくりしていってください」
邪魔をしないように、けれど耳には届くぐらいの声で別れを告げ、
扉へと向かおうとしたその時――。
- 【主人公】
- 「えっ……?」
- 【一条寺 帝歌】
- 「待て」
一条寺くんの手が、わたしの腕をぎゅっと掴んでいる。
その指先は、何故か少しだけ震えていた。
- 【主人公】
- 「一条寺……くん?」
- 【一条寺 帝歌】
- 「行かないでくれ、まだ……」
そっと彼の顔を覗くと、伏した目から伸びたまつげの影が頬に落ちていた。
どこか切なげで、苦しげな横顔……。
- 【一条寺 帝歌】
- 「俺の話を、聞いてくれるか。ただそれだけでいい」
- 【主人公】
- 「……はい」
静かに返事をすると、少しだけ安心したように息をついた。

墨ノ宮くんが試験を受ける広場に足を踏み入れると――。
一際大きな歓声が響き渡った!
- 【主人公】
- 「え……」
空中に舞い散る墨のしぶき。
それに伴い、大きな筆が踊りだす。
- 【墨ノ宮 葵】
- 「……ふっ!」
鋭い気合と共に、巨大な画仙紙の上に墨ノ宮くんが筆を走らせる。
大筆を自由自在に使いこなすその姿は、まるで優雅な舞にすら思えて。
- 【墨ノ宮 葵】
- 「……っ! は……!」
祈るようなひたむきさで一気に抜かれた筆は、真っ直ぐな軌跡を画く。
そうして出来あがったのは――『華』という見事な漢字一文字。
瞬間、文字が輝き出したかと思うと弾けるようなきらきらが勢いよく空へと放たれ――。
空を覆い尽くすような、この上なく美しく大きな赤い華が出現した。
- 【主人公】
- 「すごい……」
見るもの全てを惹きこむような赤い色。彼岸花を思わせるそれは、優美で鮮やかで艶やかで、どこか危うい。
そこから零れ落ちるきらきらは、まるで甘い花の蜜のよう。
- 【陶堂 千彫】
- 「……墨ノ宮葵、合格」
あまりの素晴らしさに言葉を失うわたしたちの耳に、陶堂先生の声が響く。
すると赤い華は空に溶け込むように消えて――墨ノ宮くんも、がくりと片膝をついた。
- 【主人公】
- 「墨ノ宮くん!」
わたしは慌てて走り寄る。

わたしの制止の声も虚しく、他の6人による魔法芸術のお披露目会が開始された。
- 【響 奏音】
- 「まずは、俺からっすね!」
響くんが笑顔でチェロを構える。
弦から生み出されるのは、あの時聞いたのと同じほっとするような温かい旋律。
キラキラと、五線譜で出来たリボンが生まれ、全員をしゅるしゅると包んでいく。
やがてリボンは金色に輝き……奏音くんが演奏を終えると同時に弾けて、光の粒が雨のように降り注いだ。
- 【帯刀 凛太郎】
- 「次はおれだ!」
帯刀先輩の掛け声に、わたしははっとして振り返る。
ノミを片手に帯刀先輩は樹をリズミカルに削り始め……あっという間に、一羽の鷲を生み出した。
たしかに樹で出来ているはずの鷲が輝き出し、力強く羽ばたき始める!
- 【庵條 瑠衣】
- 「ほらほら、こっちだよん!」
庵條先輩が差し出した腕に鷲がゆっくりと止まる。
- 【庵條 瑠衣】
- 「目を離しちゃダメだよ!」
ウィンクを1つすると、庵條先輩は踊り始めた。
足元からぶわっと白く柔らかな羽根が生まれ、庵條先輩はその中を心地よさそうに舞う。
先輩と共に舞い踊る羽根が、1枚ふんわりと土筆くんの持つキャンバスに着地した。
- 【土筆もね】
- 「きれいな白……ぼくに、ぴったり」
そう呟くと、土筆君は絵筆を走らせた。
キャンバスからアイスブルーのような硬質な光が生まれ、土筆くんの瞳がまるでガラスのように美しく輝く。
視線の先には、墨ノ宮くんがいた。
- 【墨ノ宮 葵】
- 「……見える」
墨ノ宮くんは閉じていた目を開き、アイスブルーの光を切り裂くように筆を振るう。
書で表現したのは……1匹の狼。
漆黒に輝く墨からすっと立ち上がった狼は、正面を見据えながら駆け出した!
その先にいたのは一条寺くん。
一条寺くんはぴんと伸びた姿勢のまま、恐れることなく狼を見据え……
- 【主人公】
- (ぶつかる……!?)
その瞬間、凛とした歌声が響き渡った。と同時に、あたりが眩しいほどの光に包まれる。
光が弱まった時、そこは……
- 【主人公】
- 「え、そ、空の上……!?」
たしかに星フェスハウスにいたはずなのに、わたしたちは雲の上に浮かんでいた。
驚いて振り返ると、光に包まれながら一心に歌う一条寺くんの姿があった。
- 【一条寺 帝歌】
- 「これが……俺の歌だ」

- 【帯刀 凛太郎】
- 「うっし、出来た!
使える材料があんまなかったんで、こんなもんで勘弁な!」
帯刀先輩はそう言って、わたしたちの目の前に料理を置いてくれた。
その料理は、とても大きなオムレツのようなものに、キノコのソースが添えられたものだった。
- 【主人公】
- 「こんなもん、って……すごいです! これってオムレツ……ですか?」
- 【土筆 もね】
- 「スフレオムレツ。ぼくこれ好き」
- 【帯刀 凛太郎】
- 「まあまあ、名前はなんだっていいさ。とにかく出来たてを食ってくれよ!」
- 【主人公】
- 「あっ、はい! いただきます!」
一口すくって口に入れる。
甘い、バターの香り――。
次の瞬間、ほどよい塩加減の卵が口の中でふわあっと消えていった。
なにこれ……?
- 【主人公】
- (いま、確かに卵の味がしたのに……)
わたしの口の中で、いったい何が起こったのだろう。
確認したくて、もう一口頬張る。
- 【主人公】
- 「……!!」
もう一口頬張る。
- 【帯刀 凛太郎】
- 「どうだ?美味いか?」

- 【庵條 瑠衣】
- 「……いいよ、踊ろう」
ふたりで手を繋いで、誰もいない庭へ歩みを進める。
降り注ぐ月光がライト。噴水が音楽代わり。此処がわたしたちのステージだ。
- 【主人公】
- 「満月だから、とっても明るいですね。踊るのにぴったり」
わたしがそう言うと、先輩は静かに微笑を浮かべた。
いつもより穏やかで、でもやっぱりどこか寂しそうな顔。
ゆっくりとダンスが始まる。先輩の顔をじっと見つめたまま、わたしは覚えたステップを踏む。
- 【主人公】
- (何だか、体が自由に動く)
- 【主人公】
- (先輩が次に何処へ行こうとしてるのかわかるみたい。不思議……)
- 【庵條 瑠衣】
- 「最初に思った通りだったよ。君はすごく上達が早い。
それに何より、ダンスが好きだって事がよく伝わる」
足を止めずに踊り続けていると、いつもより強く体を引き寄せられた。
- 【主人公】
- 「先輩……?」
耳元に落ちてくる、小さな小さな呟き。
- 【庵條 瑠衣】
- 「……君と踊って気付いたんだ。やっぱりオレは……」

- 【土筆もね】
- 「ぼく……寝てた? どうしてここに……?」
まだ少しぼんやりしている。どうやら、土筆くんはここに来た経緯と、眠っている間の出来事は覚えていないようだ。
- 【主人公】
- 「土筆くん、美術室で倒れたんです。
だから、とりあえずわたしもここまで一緒に……」
- 【土筆もね】
- 「で、きみずっとそこにいたの……? どういうつもり?」
- 【主人公】
- 「……ごめんなさい。でも保健の先生もいなかったし」
- 【土筆もね】
- 「だからって……! ずっといる意味がわかんない」
- 【主人公】
- 「あの……、これが……」
わたしはそっと、掴まれたままの腕を反対の手で指差す。
土筆くんは、ようやく今までわたしの腕を掴んでいた事に気が付いた。
- 【土筆もね】
- 「……っ!!」
土筆くんの白い頬が、みるみる赤くなる。
- 【土筆もね】
- 「……なんで……!」
- 【主人公】
- 「え?」
- 【土筆もね】
- 「なんでそのままじっとしてたの!?」
土筆くんは慌ててわたしを掴んでいた手を離した。
その顔は、明らかに動揺している。

- 【響奏音】
- 「じゃあ……まずは軽めに一曲……」
すうっと大きく息を吸って、響くんは目を閉じる。
そして、ダンクシュートすら簡単に決める手が弓を構えて――。
- 【主人公】
- (ああ……)
伸びやかで深みのある音色が、星フェスハウスの中に響き渡る。
心地よく、身を委ねてしまいそうになるチェロの音。
低く、低く、高く、低く。
気持ちの良い音が尾を引いては消えて。
響くんが弓を動かす度に、弦からはきらきらが放たれた。
- 【主人公】
- (これは……)
天気の良い、暖かな日。緑の木々の中を散歩するようなイメージがふと浮かぶ。
- 【主人公】
- (ああ……そうか。木漏れ日……)
柔らかく美しい音色が放つのは、新緑から零れる木漏れ日の光だった。
その光を受けながら、わたしは木々の中でも一際大きな樹に身を寄せる。
……泣きたいほどの安心感が、そこにはあった。
- 【響奏音】
- 「……ぱい。愛ヶ咲先輩」
低い、穏やかな声が耳に届く。
- 【主人公】
- 「……あ」
そこで――わたしはようやく現実へと戻った。
気付けば、響くんは演奏を終えている。
- 【響奏音】
- 「どうしました、先輩?」
チェロを構えたまま、優しい声で響くんは問い掛ける。
わたしは――

- 【一条寺帝歌】
- 「……覚えていてくれたか」
胸がいっぱいで言葉を失うわたしに、ふっと一条寺くんが微笑んだ。
- 【一条寺帝歌】
- 「お前が俺に、歌う事の本当の意味を思い出させてくれた。
あの頃、墨ノ宮と共に見つけた純粋な気持ちだ」
- 【主人公】
- 「一条寺くん、わたし……その気持ちの隣に並べるでしょうか」
わたしは、ずっと伝えられなかった気持ちをきちんと声に出した。
- 【主人公】
- 「一緒に、アルティスタ・プリンセスを目指したいです」
- 【一条寺帝歌】
- 「……もちろんだ」
まだまだ届かない、そこまで本当に行けるほどの力があるのかわからない。
けれど……何度練習を重ねても揺れていた心が、ぴたりと止まった。
わたしの行くべき道とやるべき事が、目の前でまっすぐ開けたようだった。
- 【一条寺帝歌】
- 「ひとつ頼みがあるんだが……」
わたしを見つめたまま、一条寺くんが少しだけ言い淀む。
そして――ともすれば聞き逃してしまいそうな小さな声で願った。
- 【一条寺帝歌】
- 「……俺の名を呼んでくれないか? 他の誰とも違うように……俺の名前を呼んでほしい」

墨ノ宮くんの腕に力がこもったかと思うと、わたしはその胸の中にしっかりと抱きすくめられていた。
- 【主人公】
- 「あ、あのっ!?」
突然の出来事にわたしは焦り、腕の中で小さな抵抗を繰り返す。だけど、墨ノ宮くんの力は緩む事はなかった。
- 【主人公】
- 「す、墨ノ宮くん? あの……」
- 【墨ノ宮葵】
- 「……葵って、呼んで」
- 【主人公】
- 「……え?」
- 【墨ノ宮葵】
- 「キミには、名前で呼んでほしい」
- 【主人公】
- 「な、名前でって……」
困惑するわたしに、墨ノ宮くんはへにゃりと眉を下げる。
- 【墨ノ宮葵】
- 「……嫌、かな」
体を抱き締める腕の強さと、叱られて耳を垂らす犬のようなその表情の差に、わたしの頭はくらくらした。

- 【帯刀凛太郎】
- 「そう来なくちゃ」
凛太郎さんは大人っぽく微笑むと、わたしをリードして静かにワルツのリズムに身を任せる。
- 【帯刀凛太郎】
- 「ほら……1、2、3、1、2、3……お前、上手じゃねーか」
- 【主人公】
- 「だって、体育の授業で、みんな猛特訓しましたから……」
それでも、こんなワルツを踊るのは初めての事。
しかも、相手が凛太郎さん……。
急に意識してしまい、ぼっと顔が熱くなるのを感じる。
- 【主人公】
- 「あ……っ!」
ステップが乱れて、思わず声を上げたその時。
凛太郎さんの腕が、しっかりとわたしの腰を支えてくれた。
- 【帯刀凛太郎】
- 「……集中して。ほら、おれに体をあずけて」
- 【主人公】
- 「は、い……」
楽器の音が静かに尾を引く中、夢のようなダンスが終わった。

思いも寄らないほど近くに、瑠衣先輩の顔がある。それは鼻先どころか、唇まで触れてしまいそうな距離で。
抱き寄せられた格好のまま、わたしは身動きも出来ずに息を詰めた。
音楽はまだ鳴っている。みんなも踊っている。
けれどわたしたちの周りだけ時が止まったように、見つめ合っていた。
- 【主人公】
- (……瑠衣先輩)
もし、わたしか先輩が少しでも動けば。
きっと唇が触れ合ってしまう――。
そう考えた時、先輩がゆっくりと動いた。唇に息がかかり、体温が近付いて――。
- 【主人公】
- (……!!)
ぎゅっと目を閉じたけれど、衝撃は幾ら待っても来なかった。
- 【主人公】
- 「……瑠衣先輩……?」
恐る恐る目を開けると、先輩はわたしの顔を覗き込んでいるだけで。
- 【庵條瑠衣】
- 「なーんてね! そう言う純粋なところも、すごく可愛くて好きだよ♪」
- 【主人公】
- 「か……からかったんですか……!」
- 【庵條瑠衣】
- 「違うよ、本気。返事は今すぐじゃなくてもいいけど……
予約はさせてね、マイリトルフラワー☆」
唇の横へ、柔らかいものの触れる感触。
キスされたのだと気付いた途端、わたしの頭の中は今度こそ完全に真っ白になった。

- 【土筆もね】
- 「姉弟じゃないよ……。姉弟だったらこんな事出来ない」
言うが早いか、わたしの頬にキスをした。
- 【主人公】
- 「……!」
- 【土筆もね】
- 「……ね、きみは誰のもの?」
- 【主人公】
- 「……っ」
わたしは何か答えようとも思ったが、体中が熱くなって何も言えなくなっていた。
- 【庵條瑠衣】
- 「おっと、オレったらとんだお邪魔虫だったってわけね~。
これは失礼しました☆」
庵條先輩は、こちらに向けてぱちりと優雅なウインクをすると、そのまま手を振りながら人混みの中に紛れていった。
その背を見送りながら、そっともねくんに声を掛ける。
- 【主人公】
- 「も、もねくん……庵條先輩、行ったよ」
それでも、もねくんはわたしから離れようとしない。
- 【主人公】
- 「ねえ、もねく……」
- 【土筆もね】
- 「……先輩、すごく体が熱いよ」
- 【主人公】
- 「……!」
耳元で囁かれて、思わずぴくりと肩を震わせてしまう。
くすくすと、もねくんの悪戯っぽい微笑みが聞こえた。

流れ始めた曲に合わせて、互いの体を支えながらくるくると踊る。
響くんの目にはわたしが、わたしの目には響くんしか映らない。
- 【響奏音】
- 「……俺、先輩と出会えて本当に良かった」
ダンスの最中、響くんがぽつりと呟いた。それはわたしにしか届かない、小さな声だ。
- 【響奏音】
- 「アートセッションもアンサンブルも、みんなと……先輩と奏でたからこそ成功したんです」
- 【響奏音】
- 「そうして今……チェロまで続けられる事になって……」
響くんの目が、ゆっくりと熱を帯びていく。
- 【響奏音】
- 「全部、先輩がいてくれたから……」
- 【主人公】
- 「……ううん、響くんの力だよ。わたしは少し、背中を押しただけ」
- 【主人公】
- 「響くんが、そういう人だから――あ!」
話しながら踊っていたせいだろうか、ふらりと足元がよろけて転びそうになる。それを響くんが上手に支えてくれた。
先ほどよりも寄り添う体は、ほとんど抱き締められているような状態になる。
- 【主人公】
- 「ご、ごめんね」
- 【響奏音】
- 「愛ヶ咲先輩……」
気恥かしさに離れようとすると、響くんはわたしの体をぎゅっと抱き締めて――。
ふわりと、わたしの頬にかすめるだけのキスをした。